現在では「犬を叱ることは避けるべき」という考えが主流となっています。この記事では、犬(特に噛みつく犬)を叱ることの難しさを確認するためにも、あえて「正しい犬の叱り方」について、お話ししてみたいと思います。
噛みつく、吠える…すぐに止めたい問題行動のしつけでは叱ることも必要?
愛犬と生活していると、楽しいことばかりではなく、大変なことや困ったことに頭を悩ますことも色々とあります。
特に、
◉噛みつく
◉吠える
といった愛犬の行動は、飼い主に怪我をさせてしまったり、周囲の人に迷惑をかけてしまったりと、深刻な問題を引き起こしてしまうことから、問題行動といわれることもあります。
このような問題行動を改善・矯正するためのしつけの方法として、
『時には厳しく叱る(体罰の使用も含める)ことも必要』
という考えもあります。
しかし、しつけの方法に『叱る』を組み込むことは、実はとても難しいことです。
特に、噛みつきのような攻撃的な(激しい)行動に対して叱って制止しようとすると、かえって問題を悪化させてしまうこともあります。
この記事では、
【噛みつきを叱ってしつける場合のリスク】
についてお話ししたいと思います。
特に、
◉噛みつく
◉吠える
といった愛犬の行動は、飼い主に怪我をさせてしまったり、周囲の人に迷惑をかけてしまったりと、深刻な問題を引き起こしてしまうことから、問題行動といわれることもあります。
このような問題行動を改善・矯正するためのしつけの方法として、
『時には厳しく叱る(体罰の使用も含める)ことも必要』
という考えもあります。
しかし、しつけの方法に『叱る』を組み込むことは、実はとても難しいことです。
特に、噛みつきのような攻撃的な(激しい)行動に対して叱って制止しようとすると、かえって問題を悪化させてしまうこともあります。
この記事では、
【噛みつきを叱ってしつける場合のリスク】
についてお話ししたいと思います。
正しく使えば、「叱る」は有効なしつけ方法
「叱ることのリスクについて話す」
と書いておきながら、いきなり矛盾するようなことを言いますが、ある行動(例えば噛みつき)を止めさせたい場合、実は一番即効性の高い(すぐに効果を発揮する)しつけが
《正しく(適切に)叱る》
という方法です。
叱るというのは、止めたい行動(噛みつき)を犬が起こした直後に嫌悪刺激(犬が嫌がる刺激:大きな声や音・痛み、etc)を提示することで、
「これ(噛みつき)をすると嫌なことがある」
という学習につなげて、行動を起こすこと(噛みつくこと)を無くそうとする行為です。
《正しく叱る》とは
❶タイミングと時間が適切
❷強度(声の大きさ・叩く強さ)が適切
❸アフターフォローが適切
(叱った効果の見極め・不安や恐怖を取り除く・噛まなかったことをほめる、etc)
の三つの条件を満たしていることだと、私は思っています。
図式にすると以下のようになります。
【例:ブラシをかけられるのを嫌がって噛みついてくる犬】
ブラシを身体にあてる
↓
噛みつく
↓
嫌悪刺激の瞬間的な提示(大きな音、叩く、etc)
❶適切なタイミング
❷適切な強度
↓
噛みつくのを止める
↓
再度ブラシを身体にあてる
↓
噛みつかない
↓
《噛みつかなかったこと》をほめる
❸適切なアフターフォロー
❶❷❸の三つの条件について、以下で詳しく述べていきます。
と書いておきながら、いきなり矛盾するようなことを言いますが、ある行動(例えば噛みつき)を止めさせたい場合、実は一番即効性の高い(すぐに効果を発揮する)しつけが
《正しく(適切に)叱る》
という方法です。
叱るというのは、止めたい行動(噛みつき)を犬が起こした直後に嫌悪刺激(犬が嫌がる刺激:大きな声や音・痛み、etc)を提示することで、
「これ(噛みつき)をすると嫌なことがある」
という学習につなげて、行動を起こすこと(噛みつくこと)を無くそうとする行為です。
《正しく叱る》とは
❶タイミングと時間が適切
❷強度(声の大きさ・叩く強さ)が適切
❸アフターフォローが適切
(叱った効果の見極め・不安や恐怖を取り除く・噛まなかったことをほめる、etc)
の三つの条件を満たしていることだと、私は思っています。
図式にすると以下のようになります。
【例:ブラシをかけられるのを嫌がって噛みついてくる犬】
ブラシを身体にあてる
↓
噛みつく
↓
嫌悪刺激の瞬間的な提示(大きな音、叩く、etc)
❶適切なタイミング
❷適切な強度
↓
噛みつくのを止める
↓
再度ブラシを身体にあてる
↓
噛みつかない
↓
《噛みつかなかったこと》をほめる
❸適切なアフターフォロー
❶❷❸の三つの条件について、以下で詳しく述べていきます。
正しく叱るための条件❶:適切なタイミングと時間…噛みつく瞬間をとらえられるか?

犬を正しく叱る(嫌悪刺激を提示する)場合に、タイミングはとても大切です。
適切なタイミングは
《犬が行動を起こした直後》
です。
噛みつきでいうと、
《噛もうとして歯を人に当てた瞬間》
です。
そのタイミングで嫌悪刺激(大きな声を出す・大きな音を出す・叩く、etc)を提示することで、
「人に噛みつくと嫌なことがある」
という学習をしてくれる可能性が高くなります。
とはいえ、
《噛もうとして歯を人に当てた瞬間》
を的確にとらえて叱るというのは難しいものです。
「今から噛みつきを改善するしつけに取り組もう」と心に決めて、以下のような準備ができている状況ならば、《噛もうとして歯を人に当てた瞬間》に反応して叱ることも可能です。
◎噛んできてもひるまない心構え(痛みに対する覚悟)
◎噛まれても怪我をしないような準備(丈夫な皮手袋を手にはめている、等)
しかし、どんな人も(プロのドッグトレーナーであっても)、急に犬が噛んできたらびっくりするものです。
身体的反応としては、噛まれた(噛まれそうな)部分を反射的に犬の口(歯)から遠ざけようとします。
これは生き物としての防衛反応ですから、制御することは難しいです。
犬としては、自分にとって嫌なことをするもの(人の手)を排除することが目的で噛んできますから、
噛みつく
↓
反射的に手を引っ込める
という図式が成立した時点で
「噛めば嫌なことが無くなる(排除できる)」
という学習に結びついてしまいます。
適切なタイミングは
《犬が行動を起こした直後》
です。
噛みつきでいうと、
《噛もうとして歯を人に当てた瞬間》
です。
そのタイミングで嫌悪刺激(大きな声を出す・大きな音を出す・叩く、etc)を提示することで、
「人に噛みつくと嫌なことがある」
という学習をしてくれる可能性が高くなります。
とはいえ、
《噛もうとして歯を人に当てた瞬間》
を的確にとらえて叱るというのは難しいものです。
「今から噛みつきを改善するしつけに取り組もう」と心に決めて、以下のような準備ができている状況ならば、《噛もうとして歯を人に当てた瞬間》に反応して叱ることも可能です。
◎噛んできてもひるまない心構え(痛みに対する覚悟)
◎噛まれても怪我をしないような準備(丈夫な皮手袋を手にはめている、等)
しかし、どんな人も(プロのドッグトレーナーであっても)、急に犬が噛んできたらびっくりするものです。
身体的反応としては、噛まれた(噛まれそうな)部分を反射的に犬の口(歯)から遠ざけようとします。
これは生き物としての防衛反応ですから、制御することは難しいです。
犬としては、自分にとって嫌なことをするもの(人の手)を排除することが目的で噛んできますから、
噛みつく
↓
反射的に手を引っ込める
という図式が成立した時点で
「噛めば嫌なことが無くなる(排除できる)」
という学習に結びついてしまいます。
叱るタイミングがずれると犬が間違った学習をするかも?
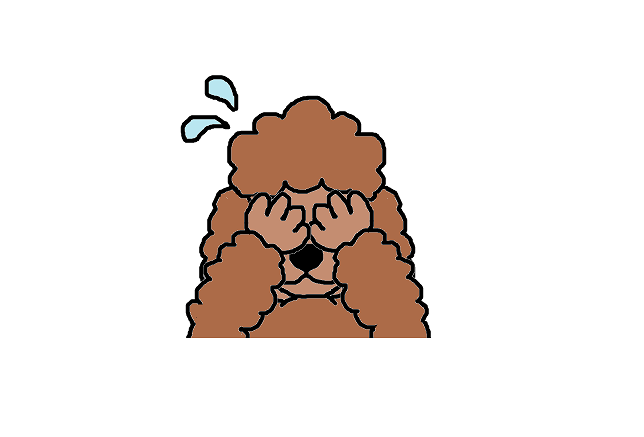
犬にとって好ましい刺激(快刺激:ほめる・オヤツをあげる、etc)であれ、嫌な刺激(嫌悪刺激)であれ、提示された刺激(この場合は叱ること)は、直前にしていた行動と結びつきます。
一度手を引っ込めた後に思い直して叱ったとしても、噛みつき行動からは数秒経過していますから、
「噛みついたから叱られた」
という学習に結びつく可能性は低くなります。
例えば、噛みついた後に人の顔に注目してる時に
◉大きな声で怒鳴る
◉大きな音を立てる(金属片を入れた缶を鳴らす、etc)
◉強く叩く
といった嫌悪刺激を提示されると、
「人の顔を見ると嫌なことがある」
という学習に結びついてしまい、ますます人のことが嫌いになってしまうかもしれません。
このような間違った学習を防ぎ
「噛みついたら叱られる」
という学習をして欲しいなら、
《噛もうとして歯を人に当てた瞬間》
に
◉大きな声で怒鳴る
◉大きな音を立てる(金属片を入れた缶を鳴らす、etc)
◉強く叩く
といった嫌悪刺激を提示しなくては効果がありません。
しかも、噛みついてきたら毎回(油断している時に噛んできた場合でも)、手を引っ込めることなく、嫌悪刺激を提示する必要があります。
一度手を引っ込めた後に思い直して叱ったとしても、噛みつき行動からは数秒経過していますから、
「噛みついたから叱られた」
という学習に結びつく可能性は低くなります。
例えば、噛みついた後に人の顔に注目してる時に
◉大きな声で怒鳴る
◉大きな音を立てる(金属片を入れた缶を鳴らす、etc)
◉強く叩く
といった嫌悪刺激を提示されると、
「人の顔を見ると嫌なことがある」
という学習に結びついてしまい、ますます人のことが嫌いになってしまうかもしれません。
このような間違った学習を防ぎ
「噛みついたら叱られる」
という学習をして欲しいなら、
《噛もうとして歯を人に当てた瞬間》
に
◉大きな声で怒鳴る
◉大きな音を立てる(金属片を入れた缶を鳴らす、etc)
◉強く叩く
といった嫌悪刺激を提示しなくては効果がありません。
しかも、噛みついてきたら毎回(油断している時に噛んできた場合でも)、手を引っ込めることなく、嫌悪刺激を提示する必要があります。
理想の叱り方(行動直後の瞬間的な嫌悪刺激の提示)は冬のドアノブの静電気?

冬の空気が乾燥している時期に、玄関や車のドアを開けるためにドアノブに手を伸ばして、
「バチッ!」
と静電気が走って、びっくりして手を引っ込めた経験、ほとんどの人が一度はしたことがあるでしょう。
そして多くの人が、
◎ドアノブに触る時に注意深くそっと手を伸ばす
◎静電気防止のグッズを利用する
というように、少なくともしばらくの間(冬が終わる頃まで)は以前と比べて、ドアを開けようとする時の行動に変化が生じる可能性が高くなります。
《ドアノブに触れる瞬間》
に静電気の「バチッ!」を味わう(瞬間的に嫌悪刺激が提示される)ことで、ドアノブに対するアプローチの仕方が変わっています。
行動直後の嫌悪刺激の提示によって行動が変わる、良い例だといえます。
犬を正しく叱る理想のタイミングが、まさに
【ドアノブを触る瞬間の静電気】
と同じです。
正しいタイミングでなおかつ瞬間的な嫌悪刺激を提示すれば、犬の行動を変えることは確かに可能です。
「ダメでしょ」
「何度言ったら分かるの?」
と、くどくどしつこく叱るのではなく
【瞬間的に嫌悪刺激を提示する】
ことが、タイミングと並んで重要です。
しかし、誰もがドアノブの静電気のような理想のタイミングで瞬間的に犬を叱れるわけではありません。
正しく叱る条件❶の
【適切なタイミングで(瞬間的に)叱る】
がいかに難しいか、お分かり頂けたでしょうか。
「バチッ!」
と静電気が走って、びっくりして手を引っ込めた経験、ほとんどの人が一度はしたことがあるでしょう。
そして多くの人が、
◎ドアノブに触る時に注意深くそっと手を伸ばす
◎静電気防止のグッズを利用する
というように、少なくともしばらくの間(冬が終わる頃まで)は以前と比べて、ドアを開けようとする時の行動に変化が生じる可能性が高くなります。
《ドアノブに触れる瞬間》
に静電気の「バチッ!」を味わう(瞬間的に嫌悪刺激が提示される)ことで、ドアノブに対するアプローチの仕方が変わっています。
行動直後の嫌悪刺激の提示によって行動が変わる、良い例だといえます。
犬を正しく叱る理想のタイミングが、まさに
【ドアノブを触る瞬間の静電気】
と同じです。
正しいタイミングでなおかつ瞬間的な嫌悪刺激を提示すれば、犬の行動を変えることは確かに可能です。
「ダメでしょ」
「何度言ったら分かるの?」
と、くどくどしつこく叱るのではなく
【瞬間的に嫌悪刺激を提示する】
ことが、タイミングと並んで重要です。
しかし、誰もがドアノブの静電気のような理想のタイミングで瞬間的に犬を叱れるわけではありません。
正しく叱る条件❶の
【適切なタイミングで(瞬間的に)叱る】
がいかに難しいか、お分かり頂けたでしょうか。
正しく叱る条件❷:適切な強度…叱り方が弱過ぎても強過ぎても副作用を招くかも?
正しく叱るためには、タイミングと同じく強度(声や音の大きさの程度、叩く時の力加減、etc)も大切です。
叱り方の例としては
◉金属を入れた缶を鳴らす(大きな音)
◉犬を直接叩く(衝撃・痛み)
といった嫌悪刺激を提示する方法があります。
ここでは特に、
《犬を直接叩く(体罰)》
という方法を取った場合を考えてみます。
「噛みついたら痛み(衝撃)を感じるから、噛みつくのは止めよう」
という学習を犬がしてくれることを期待するわけです。
図式にすると以下のようになります。
(叩くタイミングは適切だと仮定します)
犬が噛みつく
↓
直後に叩く
↓
噛みつくのを止める
この時、叩く強度が適切でなかった場合にどのような結果を招く可能性があるでしょうか。
叱り方の例としては
◉金属を入れた缶を鳴らす(大きな音)
◉犬を直接叩く(衝撃・痛み)
といった嫌悪刺激を提示する方法があります。
ここでは特に、
《犬を直接叩く(体罰)》
という方法を取った場合を考えてみます。
「噛みついたら痛み(衝撃)を感じるから、噛みつくのは止めよう」
という学習を犬がしてくれることを期待するわけです。
図式にすると以下のようになります。
(叩くタイミングは適切だと仮定します)
犬が噛みつく
↓
直後に叩く
↓
噛みつくのを止める
この時、叩く強度が適切でなかった場合にどのような結果を招く可能性があるでしょうか。
犬を叱る強度が弱すぎたら、噛みつきがひどくなる?

犬が噛みついてきた直後に叩いて叱る場合。
叱る強度が弱い(痛みや衝撃が噛みつきを制止させるまでに至らない)と、逆に犬を刺激してしまって、かえって激しく噛みつくようになってしまう可能性があります。
例えば手で叩いた強度が弱いと、かえってその手を排除しようとする行動(噛みつき)の強度が増してしまうリスクがあります。
犬の噛みつきの激しさが増すと、人が感じる恐怖や痛みが増すので、叱って噛みつきを制止することを諦める(手を引っ込める)可能性が高くなります。
犬が噛みつく
↓
直後に手で叩く(強度が弱い)
↓
より激しく噛むようになる
(手を排除しようとする行動の強度が増す)
↓
手を引っ込める
この図式が成立することで、
「噛みつくことは手を排除するためにやっぱり有効な手段」
という学習に結びつき、かえって噛みつき行動が強化されてしまいます。
火を消そうとしてふいごや団扇で風を吹きかけた時、風の強さが中途半端だと、かえって火の勢いが増してしまうのと、似ているかもしれません。
(似ていないかもしれません)
叱る強度が弱い(痛みや衝撃が噛みつきを制止させるまでに至らない)と、逆に犬を刺激してしまって、かえって激しく噛みつくようになってしまう可能性があります。
例えば手で叩いた強度が弱いと、かえってその手を排除しようとする行動(噛みつき)の強度が増してしまうリスクがあります。
犬の噛みつきの激しさが増すと、人が感じる恐怖や痛みが増すので、叱って噛みつきを制止することを諦める(手を引っ込める)可能性が高くなります。
犬が噛みつく
↓
直後に手で叩く(強度が弱い)
↓
より激しく噛むようになる
(手を排除しようとする行動の強度が増す)
↓
手を引っ込める
この図式が成立することで、
「噛みつくことは手を排除するためにやっぱり有効な手段」
という学習に結びつき、かえって噛みつき行動が強化されてしまいます。
火を消そうとしてふいごや団扇で風を吹きかけた時、風の強さが中途半端だと、かえって火の勢いが増してしまうのと、似ているかもしれません。
(似ていないかもしれません)
犬を叱る強度が強すぎたら?
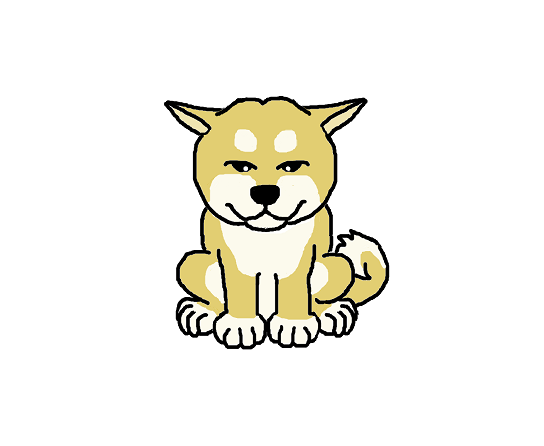
叱る強度が強すぎる場合は、どのような結果を招く可能性があるでしょうか。
まず考えられるのが、
《想定外の恐怖心を植え付けてしまう》
というものです。
◉金属を入れた缶を鳴らす(大きな音)
◉犬を直接叩く(衝撃・痛み)
とった方法の強度が強すぎた場合(音が大きすぎる・耳に近すぎる・強く叩きすぎる)、噛みついた直後の適切なタイミングでの瞬間的な嫌悪刺激の提示であっても、
★パニック状態(失禁・暴れまわる・叫び続ける、etc)を招く
★ケガをさせてしまう
という結果を招く可能性があります。
その時に感じた不安や恐怖が、
◆その時の場所や物
◆その時にいた人(叱った人)
と結びついてしまうと、
■トリミングテーブルに乗るのを嫌がる
■ブラシを見ただけで逃げる
■飼い主のことが嫌いになる
(自分から近づかなくなる・触られそうになると逃げる、etc)
という、想定外の結果を招いてしまう可能性もあります。
特に、
◎トイプードル
◎チワワ
◎ミニチュアピンシャー
といった小型犬はちょっとしたことで怪我をしやすいので、叩く方法(体罰)を選択する場合は、
《噛みつきを制止するには十分》
《ケガは負わせない&過度な恐怖は与えない》
の両方をクリアするための、絶妙な力加減が求められます。
噛みついた直後にタイミング良くに嫌悪刺激を提示できたとしても、強度が適切でなければ、期待するような効果を得られないばかりか、
◉噛みつきが激しくなる
◉飼い主のことを避けるようになる
といった、生活に支障をきたすような副作用を招く可能性があるということを、知っておくべきだと思います。
まず考えられるのが、
《想定外の恐怖心を植え付けてしまう》
というものです。
◉金属を入れた缶を鳴らす(大きな音)
◉犬を直接叩く(衝撃・痛み)
とった方法の強度が強すぎた場合(音が大きすぎる・耳に近すぎる・強く叩きすぎる)、噛みついた直後の適切なタイミングでの瞬間的な嫌悪刺激の提示であっても、
★パニック状態(失禁・暴れまわる・叫び続ける、etc)を招く
★ケガをさせてしまう
という結果を招く可能性があります。
その時に感じた不安や恐怖が、
◆その時の場所や物
◆その時にいた人(叱った人)
と結びついてしまうと、
■トリミングテーブルに乗るのを嫌がる
■ブラシを見ただけで逃げる
■飼い主のことが嫌いになる
(自分から近づかなくなる・触られそうになると逃げる、etc)
という、想定外の結果を招いてしまう可能性もあります。
特に、
◎トイプードル
◎チワワ
◎ミニチュアピンシャー
といった小型犬はちょっとしたことで怪我をしやすいので、叩く方法(体罰)を選択する場合は、
《噛みつきを制止するには十分》
《ケガは負わせない&過度な恐怖は与えない》
の両方をクリアするための、絶妙な力加減が求められます。
噛みついた直後にタイミング良くに嫌悪刺激を提示できたとしても、強度が適切でなければ、期待するような効果を得られないばかりか、
◉噛みつきが激しくなる
◉飼い主のことを避けるようになる
といった、生活に支障をきたすような副作用を招く可能性があるということを、知っておくべきだと思います。
正しく叱る条件❸:適切なアフターフォロー…叱った後の接し方が大切
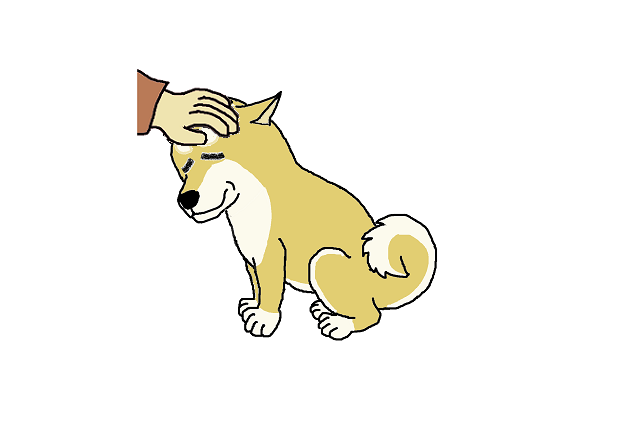
叱る(特に体罰)ことについて語る場合、
◉叩く
◉リードを強く引く
といった
『叱る(体罰を使用する)行為そのもの』
にフォーカスを当てて、
「倫理的に正しくない」
「科学的ではない」
「犬のメンタルに悪影響を与える」
「飼い主と犬の関係が悪化する」
という議論が繰り広げられるケースが多いように感じます。
ここまでお話ししてきた
◎適切なタイミング
◎適切な強度
◎瞬間的な提示
をクリアする叱り方をしたとしても、行為そのものだけを見た場合、上記のような批判を受ける可能性が高いと思われます。
しかし、叱ることを取り入れた犬のしつけを成功させるためには、
『叱る(体罰を使用する)行為そのもの』
と同じくらい、もしくはそれ以上に
【叱った後の犬への接し方(適切なアフターフォロー)】
がとても大切になります。
《叱ったら叱りっぱなし》
にするのではなく
☆犬のメンタルの状態はどうか
☆犬にケガはないか
☆叱った効果がどの程度見受けられるか
(同じことをしても噛みつかないか)
といった点に目を配って確認し、適切に対処する必要があります。
◉叩く
◉リードを強く引く
といった
『叱る(体罰を使用する)行為そのもの』
にフォーカスを当てて、
「倫理的に正しくない」
「科学的ではない」
「犬のメンタルに悪影響を与える」
「飼い主と犬の関係が悪化する」
という議論が繰り広げられるケースが多いように感じます。
ここまでお話ししてきた
◎適切なタイミング
◎適切な強度
◎瞬間的な提示
をクリアする叱り方をしたとしても、行為そのものだけを見た場合、上記のような批判を受ける可能性が高いと思われます。
しかし、叱ることを取り入れた犬のしつけを成功させるためには、
『叱る(体罰を使用する)行為そのもの』
と同じくらい、もしくはそれ以上に
【叱った後の犬への接し方(適切なアフターフォロー)】
がとても大切になります。
《叱ったら叱りっぱなし》
にするのではなく
☆犬のメンタルの状態はどうか
☆犬にケガはないか
☆叱った効果がどの程度見受けられるか
(同じことをしても噛みつかないか)
といった点に目を配って確認し、適切に対処する必要があります。
犬を叱った効果・犬のメンタル状態に合わせて、ほめてあげたり、気分転換したり…【嫌悪刺激と快刺激】をセットで提示する

ここでもう一度、ブラシをかけられるのを嫌がって噛みついてくる犬を叱る場面を例にして図式にしてみます
ブラシを身体にあてる
↓
噛みつく
↓
嫌悪刺激の瞬間的な提示(大きな音、叩く、etc)
❶適切なタイミング
❷適切な強度
↓
噛みつくのを止める
↓
再度ブラシを身体にあてる
↓
噛みつかない
↓
噛みつかなかったことをほめる
❸適切なアフターフォロー
図式の最後の部分
【噛みつかなかったことをほめる】
がとても大切です。
噛みついてきた瞬間に
❶適切なタイミング
❷適切な強度
で叱ることが出来たとしても、それが
「人に噛みついたら嫌なことがある」
という学習に結びつかなければ、意味がありません。
学習に結びついたかどうかを確認するために、噛みつき行動を誘発すること(ブラシを犬の身体にあてる)を再度やってみます。
その際に犬が噛みついてきたとしたら、
◉叱るタイミングが悪かった
◉叱る強度が弱かった
という可能性があるので、(好ましいことではありませんが)叱る行為を繰り返します。
犬が噛んでこなかったとしたら、叱ったことが
「人に噛みついたら嫌なことがある」
という学習に結びついて、噛みつき行動の発現が抑制された(噛みつくのを我慢した)可能性が高いです。
そして、ブラシを身体にあてても噛みつくのを我慢したことに対して
☆ほめる
☆オヤツをあげる
といった、犬にとって良いこと(快刺激)を提示することで、
「噛みつくのを我慢してブラシを受け入れれば良いことがある(我慢した方が得)」
という学習に結びついて、少しずつブラシングが出来るようになることが期待できます。
もしもブラシをあてた時、噛みつくのは我慢しているものの、
◉身体が震えている
◉逃げようとする
といった様子を犬が見せる場合は、叱る(叩く)強度がやや強過ぎたことで、不安や恐怖を過度に感じている可能性があります。
その場合は、
☆穏やかな声で長くほめてあげる
☆無理をせずブラシングを止める
という対応をしてあげます。
☆散歩に連れて行く
☆好きなオモチャで遊ぶ
といったことで気分転換をさせてあげるのも、アフターフォローとしては有効です。
叱った後の犬の
◎学習状況
◎メンタル状態
に合わせて適切な対応(アフターフォロー)をしてあげることが欠かせません。
ブラシを身体にあてる
↓
噛みつく
↓
嫌悪刺激の瞬間的な提示(大きな音、叩く、etc)
❶適切なタイミング
❷適切な強度
↓
噛みつくのを止める
↓
再度ブラシを身体にあてる
↓
噛みつかない
↓
噛みつかなかったことをほめる
❸適切なアフターフォロー
図式の最後の部分
【噛みつかなかったことをほめる】
がとても大切です。
噛みついてきた瞬間に
❶適切なタイミング
❷適切な強度
で叱ることが出来たとしても、それが
「人に噛みついたら嫌なことがある」
という学習に結びつかなければ、意味がありません。
学習に結びついたかどうかを確認するために、噛みつき行動を誘発すること(ブラシを犬の身体にあてる)を再度やってみます。
その際に犬が噛みついてきたとしたら、
◉叱るタイミングが悪かった
◉叱る強度が弱かった
という可能性があるので、(好ましいことではありませんが)叱る行為を繰り返します。
犬が噛んでこなかったとしたら、叱ったことが
「人に噛みついたら嫌なことがある」
という学習に結びついて、噛みつき行動の発現が抑制された(噛みつくのを我慢した)可能性が高いです。
そして、ブラシを身体にあてても噛みつくのを我慢したことに対して
☆ほめる
☆オヤツをあげる
といった、犬にとって良いこと(快刺激)を提示することで、
「噛みつくのを我慢してブラシを受け入れれば良いことがある(我慢した方が得)」
という学習に結びついて、少しずつブラシングが出来るようになることが期待できます。
もしもブラシをあてた時、噛みつくのは我慢しているものの、
◉身体が震えている
◉逃げようとする
といった様子を犬が見せる場合は、叱る(叩く)強度がやや強過ぎたことで、不安や恐怖を過度に感じている可能性があります。
その場合は、
☆穏やかな声で長くほめてあげる
☆無理をせずブラシングを止める
という対応をしてあげます。
☆散歩に連れて行く
☆好きなオモチャで遊ぶ
といったことで気分転換をさせてあげるのも、アフターフォローとしては有効です。
叱った後の犬の
◎学習状況
◎メンタル状態
に合わせて適切な対応(アフターフォロー)をしてあげることが欠かせません。
まとめ
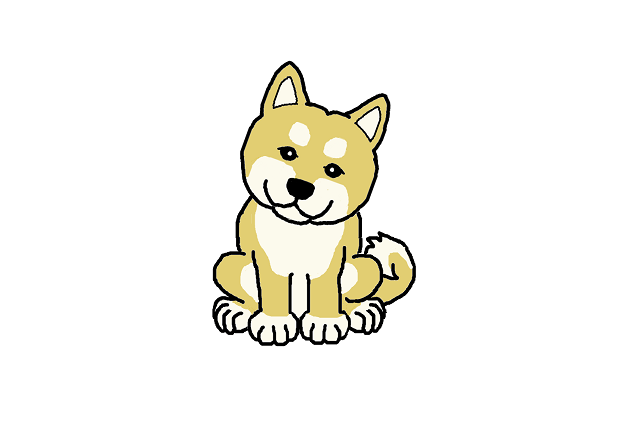
犬のしつけについて
「(体罰を含め)叱ることも必要」
と思うのか
「しつけで叱るのは絶対に避けるべき」
と思うのかは、個人の価値観によって異なるでしょうから、どちらが正しいかを明言することは出来ません。
叱ることをしつけに取り入れるかどうかは、飼い主さん各々が自由に判断すべきことだと思います。
ただ、ここまで長々と述べてきたように『叱る』という行為は
【嫌悪刺激の提示】
(❶適切なタイミング&瞬間的)
(❷適切な強度)
+
【❸適切なアフターフォロー】
の三つの条件がセットになってはじめて完成します。
特にないがしろにされがちなのが
【❸適切なアフターフォロー】
です。
嫌悪刺激の提示で終わる(叱りっぱなし)だけでは、期待した効果が得られないだけでなく、飼い主と愛犬との関係性を壊してしまうような、想定外の副作用を招くリスクがあることを、知っておくべきでしょう。
そして大前提として
【飼い主と犬との間に良好な関係が築けている(犬が飼い主のことが好き)】
が欠かせないということも、付け加えておきます。
※参考記事
↓
「(体罰を含め)叱ることも必要」
と思うのか
「しつけで叱るのは絶対に避けるべき」
と思うのかは、個人の価値観によって異なるでしょうから、どちらが正しいかを明言することは出来ません。
叱ることをしつけに取り入れるかどうかは、飼い主さん各々が自由に判断すべきことだと思います。
ただ、ここまで長々と述べてきたように『叱る』という行為は
【嫌悪刺激の提示】
(❶適切なタイミング&瞬間的)
(❷適切な強度)
+
【❸適切なアフターフォロー】
の三つの条件がセットになってはじめて完成します。
特にないがしろにされがちなのが
【❸適切なアフターフォロー】
です。
嫌悪刺激の提示で終わる(叱りっぱなし)だけでは、期待した効果が得られないだけでなく、飼い主と愛犬との関係性を壊してしまうような、想定外の副作用を招くリスクがあることを、知っておくべきでしょう。
そして大前提として
【飼い主と犬との間に良好な関係が築けている(犬が飼い主のことが好き)】
が欠かせないということも、付け加えておきます。
※参考記事
↓
☞「叱るしつけ」は難しい…愛犬を叱る時の注意点や、避けるべき理由とは?
質問や悩み相談をお寄せください
「うちの子の悩みも聞いて欲しい」
「こんな場合はどうしたら良いの?」
等々、質問したいことや相談したいことはありませんか?
佐々木ドッグトレーニングでは、飼い主さんからの質問や相談を随時受け付けています。
「こんなこと聞いても良いの?」
というささいなことでも構いません。
メールでの相談は無料ですので、お問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。
「こんな場合はどうしたら良いの?」
等々、質問したいことや相談したいことはありませんか?
佐々木ドッグトレーニングでは、飼い主さんからの質問や相談を随時受け付けています。
「こんなこと聞いても良いの?」
というささいなことでも構いません。
メールでの相談は無料ですので、お問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。


